優秀な知能や特殊な才能を持つ者が同一家系に輩出することはよく知られている。
また、逆に精神発達遅滞、もしくは精神薄弱(知的障害)の一部に遺伝要因(ここでは多因子遺伝を意味する)が存在することは、家系研究や双生児研究によって明らかにされている。知能(知能テストによるIQ、偏差値、粗点などを用いて)に関する双生児研究は、比較的多くあるが、学業成績に関するそれは数少なく、代表的研究はいままでに四つある。それらは、ドイツのFrischeisen-Kohler(1930)、スウェーデンのHusen(1960)、日本の岩下(1956)、副島(1972)らの研究である。それらの研究は用いた資料や分析方法に差異があるが、得られた共通の結論は、学業成績にも遺伝要因が認められるということである。遺伝子型が同一である一卵性ふたご(MZ)同士の方が、同胞と同じ程度の違いのある二卵性ふたご(DZ)同士よりも、2人が同一の生育環境にあったとして、学業成績の相関が高いこと、あるいは学業成績の差が少ないことが示されている。われわれはふたごの学業成績について調査研究を進めているが、それらの一端を紹介し、いままでの研究報告と比較してみたいと思う。
今回、ここに発表する資料は、1971年度と1972年度に東京大学教育学部附属中学に入学した生徒の学業成績である。ふたごの組は、1971年度入学者MZ17組(男男7組、女女10組)、1972年度入学者MZ16組(男男10組、女女6組)、DZ5組(男男3組、女女2組)である。学業成績は、前期中間と後期中間は100点満点の粗点(100点法)により、前期末と後期末は5段階評価(5点法)によりあたえられている。以上の四つの学年ごとの成績結果が、5年間(中1より高2)にわたって得られている。分析した教科は、国語、社会、数学、理科、英語、保健体育、芸術、技術家庭の8教科である。
このようにして、全教科の項目数は1971年入学者については189、1972年度入学者については188得られた。DZの組数が少ないので、血縁のないrandom pair をつくり、MZ pairとの比較に用いた。
まず、項目ごとに級内相関係数を求め、MZ pair とrandom pairのそれらの分布について、1971年度と1972年の2年度分の比較検討を行なった。Random pair の作製法を簡単に説明しておく。A、Bをふたごのpair とし、例えば1971年度分の場合、それぞれ1から17までA(1,2,…,17)、B(1,2,…,17)としておき、Aを固定してBの整数のいれかえを行ない、対応するA、Bの違う組み合せをつくればよい。電算機により乱数発生(RANSU,0≦RANSU≦1)を行ない、M=1、N=17とするとMN=M+(RANSU)×(N-M)は1≦MN≦17をとるから、順次MNを発生させ、例えば1のとき17であれば2と17をいれかえるというようにして、17回のいれかえをさせるとひとつの組合せができる。全部のA、Bが違っていなければ、同じことをA、Bの整数の違う組合せができるまで行なう。今の場合、119回目の組合せでA(1,2,…,17)に対応してB(13,1,12,17,2,10,6,3,4,8,5,14,7,15,16,9,11)ができ、A、Bのrandom pair がつくられた。
第1図は、1971年度入学者の17組のMZ pair とrandom pairの全教科に関する級内相関係数の分布を示す。それぞれ平均、標準偏差、歪度、尖度、Z1(歪度の検定値)、Z2(尖度の検定値)、最大値、最小値も示してある。Z1、Z2の値の絶対値が1.96(5%)、2.57(1%)より大きいと有意であることを示す。第2図は、1972年度入学者の16組のMZ pairと21組のrandom pair(5組の二卵性ふたごも用いた)の全教科に関する級内相関係数の分布である。両年度に関して次のことがいえる。MZ pair の級内相関係数の平均値は0.5前後、歪度は有意な負の値を持っていること、および、random pair の平均はほとんど0に近い値を持ち、歪度、尖度とも正規性分布である。以上のように、両年度に関して共通の所見が得られたから、学業成績に影響をあたえる共通の要因の存在が推定される。
今回、ここに発表する資料は、1971年度と1972年度に東京大学教育学部附属中学に入学した生徒の学業成績である。ふたごの組は、1971年度入学者MZ17組(男男7組、女女10組)、1972年度入学者MZ16組(男男10組、女女6組)、DZ5組(男男3組、女女2組)である。学業成績は、前期中間と後期中間は100点満点の粗点(100点法)により、前期末と後期末は5段階評価(5点法)によりあたえられている。以上の四つの学年ごとの成績結果が、5年間(中1より高2)にわたって得られている。分析した教科は、国語、社会、数学、理科、英語、保健体育、芸術、技術家庭の8教科である。
このようにして、全教科の項目数は1971年入学者については189、1972年度入学者については188得られた。DZの組数が少ないので、血縁のないrandom pair をつくり、MZ pairとの比較に用いた。
まず、項目ごとに級内相関係数を求め、MZ pair とrandom pairのそれらの分布について、1971年度と1972年の2年度分の比較検討を行なった。Random pair の作製法を簡単に説明しておく。A、Bをふたごのpair とし、例えば1971年度分の場合、それぞれ1から17までA(1,2,…,17)、B(1,2,…,17)としておき、Aを固定してBの整数のいれかえを行ない、対応するA、Bの違う組み合せをつくればよい。電算機により乱数発生(RANSU,0≦RANSU≦1)を行ない、M=1、N=17とするとMN=M+(RANSU)×(N-M)は1≦MN≦17をとるから、順次MNを発生させ、例えば1のとき17であれば2と17をいれかえるというようにして、17回のいれかえをさせるとひとつの組合せができる。全部のA、Bが違っていなければ、同じことをA、Bの整数の違う組合せができるまで行なう。今の場合、119回目の組合せでA(1,2,…,17)に対応してB(13,1,12,17,2,10,6,3,4,8,5,14,7,15,16,9,11)ができ、A、Bのrandom pair がつくられた。
第1図は、1971年度入学者の17組のMZ pair とrandom pairの全教科に関する級内相関係数の分布を示す。それぞれ平均、標準偏差、歪度、尖度、Z1(歪度の検定値)、Z2(尖度の検定値)、最大値、最小値も示してある。Z1、Z2の値の絶対値が1.96(5%)、2.57(1%)より大きいと有意であることを示す。第2図は、1972年度入学者の16組のMZ pairと21組のrandom pair(5組の二卵性ふたごも用いた)の全教科に関する級内相関係数の分布である。両年度に関して次のことがいえる。MZ pair の級内相関係数の平均値は0.5前後、歪度は有意な負の値を持っていること、および、random pair の平均はほとんど0に近い値を持ち、歪度、尖度とも正規性分布である。以上のように、両年度に関して共通の所見が得られたから、学業成績に影響をあたえる共通の要因の存在が推定される。
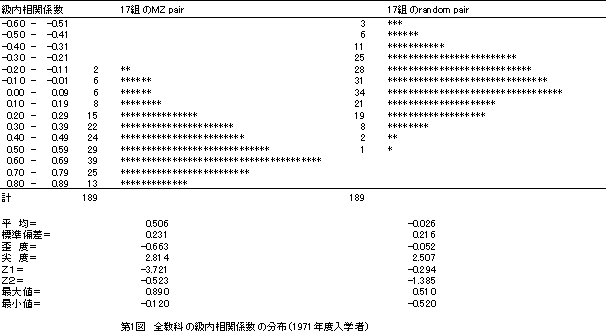
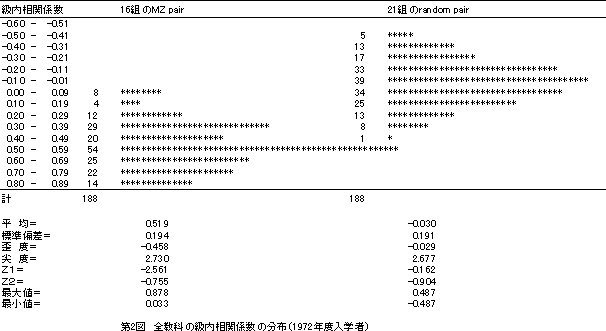
さて、この両年度を含む6年度分(1967~1972年度入学者)の知能テスト(田中-B、中1時施行)の結果が得られているが(第3図、第4図)、93組の一卵性ふたごの級内相関係数は0.632で統計学的に有意であり、22組の二卵性ふたごのそれは0.403で有意ではない。したがって、知能テストの得点には遺伝要因が関与していることは明らかである。なお、第3,4図の相関図のX軸は出生順位第1子、Y軸は第2子の知能テストの偏差値により表わしたものである。
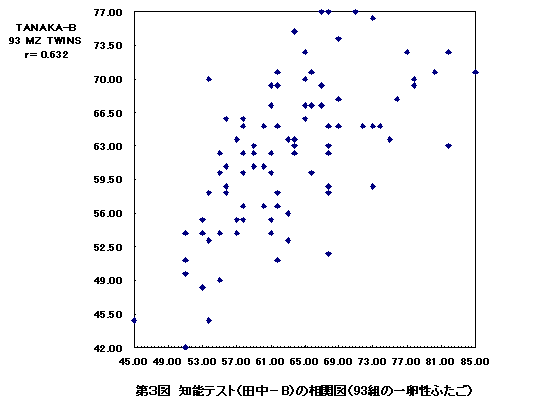
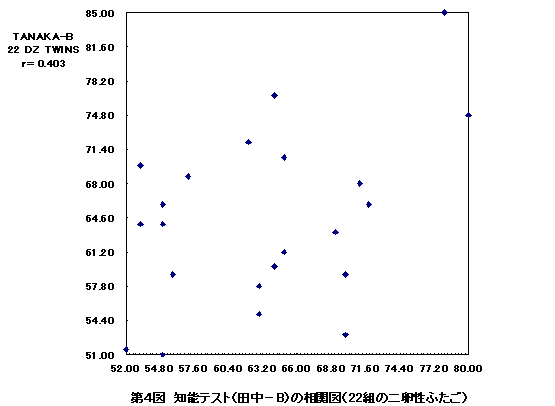
一方、知能テストの得点と学業成績は高い相関のあることが知られているので、学業成績に影響をあたえる遺伝要因の存在も容易に推定できるところである。第5,6図は、2年度分をプールしたものである。第5図は17組と16組のMZ pair に関する全教科の級内相関係数の分布であり、377項目のうち統計学に有意な項目は225ある。第6図は17組と21組のrandom pair に関する分布であるが、統計学的有意を示す項目はただのひとつである。これらの事実は上述の学業成績に関する遺伝要因の存在を支持するものであろう。
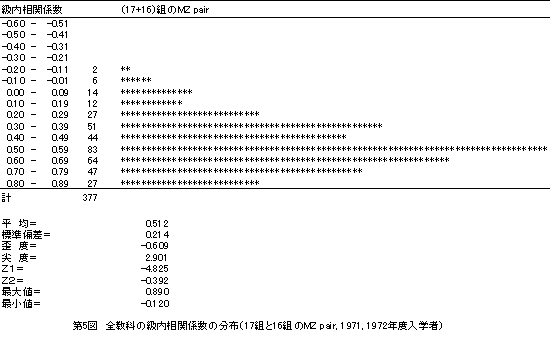
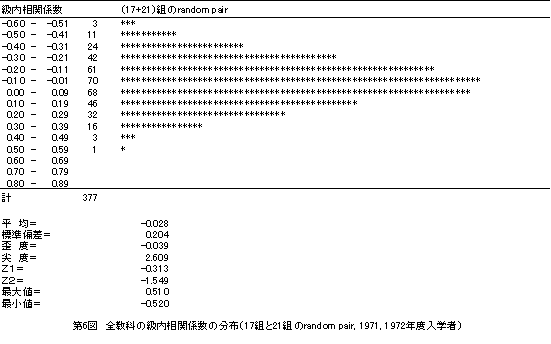
つぎに、2年度分をプールした一卵性ふたごのデータについて、教科別の比較をしてみよう(第1表)。8教科について級内相関係数の平均値で示してある。カッコの中は得られた相関係数値の数である。
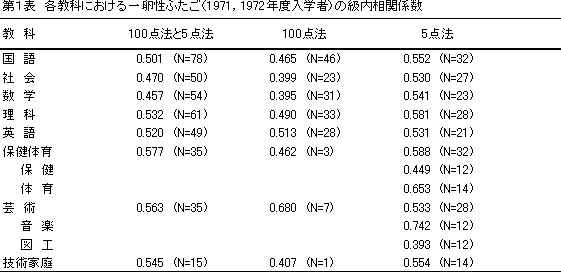
主要教科の5教科について、100点法と5点法を合わせたものをみると、相関係数の高い順に理科(0.532)、英語(0.520)、国語(0.501)、社会(0.470)、数学(0.457)となっており、理科が高く、数学が低いという特長がみられる。100点法による値、5点法による値もほぼ同じ傾向を示している。数学の級内相関係数が他の教科に比べて低いことは、同じ分析方法を用いた副島、Husenによって指摘されている。すなわち、数学の学業成績は環境要因の影響が大きいということである。このことは、後に述べるように、他の分析方法を用いた岩下、Frischeisen-Kohler の研究によっても支持されている。
主要科目以外の保健体育、芸術はいずれも高い級内相関係数を示しているが、5点法による結果をみると、保健体育のうち筆記による保健の方(0.449)が実技による体育(0.653)よりも級内相関係数の値は低い。また、芸術のうち、音楽の方(0.742)が図工(0.393)に比べて著しく高い値を示していることは興味深い。
今回の研究資料は、各項目毎のふたごの組数の差はほとんどないので、算術平均を代表値として検討してきた。多数個の相関係数(r)が同じρからのものであるという仮定を検定すること、および、それらを結合して一つの推定値を求める方法がある。それを用いて得た結果を、第1表の教科毎にρの値を示すと順に、国語(0.526)、社会(0.507)*、数学(0.489)、理科(0.554)、英語(0.551)、保健体育(0.613)、芸術(0.609)*、技術家庭(0.593)である。*印のついている社会と芸術についてはρの存在が棄却されたものであり、それらは異質な下位教科を持つのがその一因であると思われる。第2表は今回の研究対象となった生徒の小学1年から高校3年に至る身体計測値(身長、体重、胸囲、座高)の、一卵性ふたごの級内相関係数を示したものである。カッコ内は組数を示す。中学以降の組は今回の研究対象と同一である。表にみられるごとく、大多数の値は0.8~0.9台の高い値であり、すでに知られているように身体計測値の遺伝規定性を示すものである。これに較べて、いままで述べてきた学業成績の相関係数値をみると、身体計測値のそれにおよぶものはすくなく、学業成績には環境要因の影響も大であることが知れよう。
主要科目以外の保健体育、芸術はいずれも高い級内相関係数を示しているが、5点法による結果をみると、保健体育のうち筆記による保健の方(0.449)が実技による体育(0.653)よりも級内相関係数の値は低い。また、芸術のうち、音楽の方(0.742)が図工(0.393)に比べて著しく高い値を示していることは興味深い。
今回の研究資料は、各項目毎のふたごの組数の差はほとんどないので、算術平均を代表値として検討してきた。多数個の相関係数(r)が同じρからのものであるという仮定を検定すること、および、それらを結合して一つの推定値を求める方法がある。それを用いて得た結果を、第1表の教科毎にρの値を示すと順に、国語(0.526)、社会(0.507)*、数学(0.489)、理科(0.554)、英語(0.551)、保健体育(0.613)、芸術(0.609)*、技術家庭(0.593)である。*印のついている社会と芸術についてはρの存在が棄却されたものであり、それらは異質な下位教科を持つのがその一因であると思われる。第2表は今回の研究対象となった生徒の小学1年から高校3年に至る身体計測値(身長、体重、胸囲、座高)の、一卵性ふたごの級内相関係数を示したものである。カッコ内は組数を示す。中学以降の組は今回の研究対象と同一である。表にみられるごとく、大多数の値は0.8~0.9台の高い値であり、すでに知られているように身体計測値の遺伝規定性を示すものである。これに較べて、いままで述べてきた学業成績の相関係数値をみると、身体計測値のそれにおよぶものはすくなく、学業成績には環境要因の影響も大であることが知れよう。

さて、分析方法として級内相関係数の他に、ふたご間の差(対差)をみる方法がある。Frischeisen-Kohler、岩下、副島らがすでに用いた方法である。Frischeisen-Kohlerは、ふたごの2人の平均値からの偏りを対差とした。ふたごの成績をA、Bとすれば対差=A-(A+B)/2または(A+B)/2-B=1/2・(A-B)である。Frischeisen-Kohlerは学年毎に上記対差の絶対値を求め、岩下は符号を考慮して学年毎(小学3~6年、中学1~2年)に対差を算出している。副島は両方法を準用している。
これら三つの研究の対象は小、中学校の生徒であり(Frischeisen-Kohlerの対象には一部高等学校に相当する生徒が含まれているが、その数は極めてすくない)、評点はすべて5点法によるものである。それらの評価者も同一でない。われわれの研究の特色は、高等学校の生徒を含んでいること、評点は同一の問題、同一の評価者によってなされていることである。しかし、ふたごの組数がすくないので、1学年4回得られている学業成績毎に対差を算出した。5点法と100点法が混合しているので、さきに述べた377項目すべてを標準化し(Z値、Z=(X-X)/SD)、ふたご間の差の絶対値(|A-B|)を対差とした。
岩下の研究は、1948年から1954年にかけて東京大学教育学部附属中学に入学した生徒を対象としているので、岩下の結果(小、中学校)とわれわれの結果(中学校、高等学校)とを対照しつつ、小学校、中学校、高等学校の経年的変化に焦点を合わせて、以下、結果の一部を述べることにする。
第3表は、33組のMZ pair(男男17組、女女16組の1971、1972年度入学者)の中学校(中1~中3)、高等学校(高1~高2)における学業成績の対差を、教科別および全教科、男女別および男女ともについて示したものである。Random pair は33組のMZ pair よりつくり、同様に対差を算出した。参考のために入試の得点に関する対差も示してある。中学校、高等学校の男女を含めての全教科についてのMZ pairの対差平均は0.671である。それに対応するRandom pairのそれは1.167である。遺伝子型が同一で、それ以外の環境もほぼ同一と考えられるMZ pair の対差平均が、遺伝子型も環境も異なるrandom pairの対差平均より著しく小さく、約1/2になっているのは当然である。
これら三つの研究の対象は小、中学校の生徒であり(Frischeisen-Kohlerの対象には一部高等学校に相当する生徒が含まれているが、その数は極めてすくない)、評点はすべて5点法によるものである。それらの評価者も同一でない。われわれの研究の特色は、高等学校の生徒を含んでいること、評点は同一の問題、同一の評価者によってなされていることである。しかし、ふたごの組数がすくないので、1学年4回得られている学業成績毎に対差を算出した。5点法と100点法が混合しているので、さきに述べた377項目すべてを標準化し(Z値、Z=(X-X)/SD)、ふたご間の差の絶対値(|A-B|)を対差とした。
岩下の研究は、1948年から1954年にかけて東京大学教育学部附属中学に入学した生徒を対象としているので、岩下の結果(小、中学校)とわれわれの結果(中学校、高等学校)とを対照しつつ、小学校、中学校、高等学校の経年的変化に焦点を合わせて、以下、結果の一部を述べることにする。
第3表は、33組のMZ pair(男男17組、女女16組の1971、1972年度入学者)の中学校(中1~中3)、高等学校(高1~高2)における学業成績の対差を、教科別および全教科、男女別および男女ともについて示したものである。Random pair は33組のMZ pair よりつくり、同様に対差を算出した。参考のために入試の得点に関する対差も示してある。中学校、高等学校の男女を含めての全教科についてのMZ pairの対差平均は0.671である。それに対応するRandom pairのそれは1.167である。遺伝子型が同一で、それ以外の環境もほぼ同一と考えられるMZ pair の対差平均が、遺伝子型も環境も異なるrandom pairの対差平均より著しく小さく、約1/2になっているのは当然である。
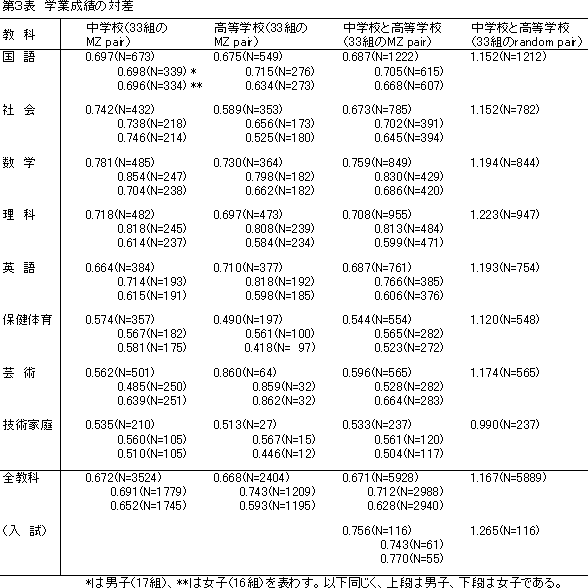
今回のわれわれの研究には残念ながら二卵性ふたごの組数が極めてすくないので、対差の計算に利用することができなかった。別々に生育した一卵性ふたごや、同じ環境に一緒に生育した他人のpairについての研究もないので、遺伝要因と環境要因の学業成績への影響の程度は不明であるが、いままでの研究結果によると、遺伝要因の存在を無視できないことは明らかにされている。例えば、岩下の研究では一卵性ふたごの小学校の全教科の対差平均は0.14、二卵性ふたごのそれは0.24、random pair のそれは0.55であった。われわれの学業成績はすべて平均0、標準偏差1に標準化してあるから、一卵性ふたごの差(0.671)は1標準偏差以内にあり、random pair のそれ(1.167)は1標準偏差をこえている。
中学校と高等学校の男女を一緒にした教科別の特長をみてみると(第7図、第3表)、対差は数学、理科において高く、保健体育、芸術、技術家庭において低く、国語、社会、英語はその中間の値である。数学の対差平均の値が高いことは、Frischeisen-Kohlerによって最初に指摘され、岩下の小、中学校、副島の中学における研究結果もそれを支持している。われわれの研究結果もそれらの研究結果と全く一致しており、数学の学業成績が最も環境の影響をうけやすいことを示唆している。保健体育、芸術の対差平均が低いことは、Frischeisen-Kohler、岩下の結果とも一致しており、これらの学業成績に関しては、より強い遺伝規定性が働いていることを物語っている。
中学校と高等学校の男女を一緒にした教科別の特長をみてみると(第7図、第3表)、対差は数学、理科において高く、保健体育、芸術、技術家庭において低く、国語、社会、英語はその中間の値である。数学の対差平均の値が高いことは、Frischeisen-Kohlerによって最初に指摘され、岩下の小、中学校、副島の中学における研究結果もそれを支持している。われわれの研究結果もそれらの研究結果と全く一致しており、数学の学業成績が最も環境の影響をうけやすいことを示唆している。保健体育、芸術の対差平均が低いことは、Frischeisen-Kohler、岩下の結果とも一致しており、これらの学業成績に関しては、より強い遺伝規定性が働いていることを物語っている。
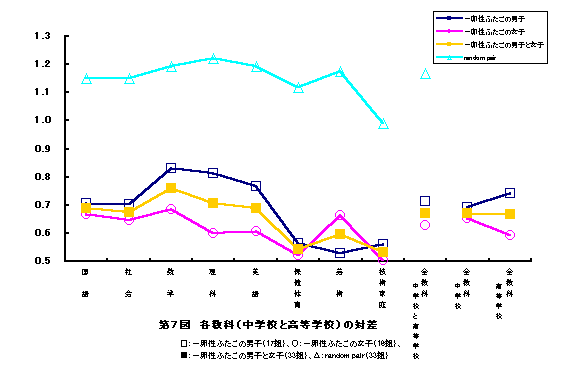
男女別にみてみると、芸術を除いては、いずれの教科も男子の対差の方が女子より大きい、男子の対差が女子より大きいことは、岩下の小・中学校における結果と一致している。男女を混合してみた場合、全教科について中学と高校を比較すると、中学(0.672)より高校(0.668)の対差が僅かながら小さくなっている。8教科のうち、英語、芸術を除き、6教科において対差は中学から高校にかけて下降している。岩下によれば小学校から中学校にかけて全教科の対差は0.14から0.21に上昇している。したがって、一卵性ふたごの学業成績の対差は小学校から中学にかけて上昇するが、中学校から高等学校にかけては下降するのであろうか。
しかし、以下のように男子と女子を別々にみていくと、いま述べたことはみかけ上のことで、男子と女子の対差の推移はそれぞれ特長のあることが分るのである。岩下の結果によると、小学校から中学校にかけて男子は0.16から0.22(その差0.06)、女子は0.11から0.20(その差0.09)で、女子の対差の上昇が著しい。本研究結果を男女別にみると、全教科について男子は0.691(中学校)から0.743(高等学校)へと対差は大きくなっているのに対し、女子では0.652(中学)から0.593(高校)へと小さくなっているのが対照的である(第7図の右)。男子では中学から高校にかけて対差が上昇しているのは8教科中4教科、下降しているのが4教科である。女子では8教科中7教科の対差が下降している。
岩下の結果と今回の研究結果をつなげて、小学校、中学校、高等学校へと対差の変化を推定してみると、男は小学校、中学校、高等学校へと漸次対差が上昇していき、しかも常に女子より大きい値を保っている。女子は小学校から中学校にかけて対差の上昇があり、しかもそれは男子の上昇率より高く、小学校の時の差より縮まるが、高校になるとむしろ対差は減少し、男子との差は大きくなる。
以上の、小学校、中学校、高等学校における学業成績の対差の男女差を含めた推移は、どう説明したらよいのだろうか。対差の男女差について、岩下は、ひとつは男女の性格の差によるものではないかと述べている。男子の場合、ふたごのおたがいが個性的で独自性が強ければ、学業成績の対差が大きくなることが予想される。さらに、岩下は当時の日本社会の男子専制の封建制が女子をして遺伝のからに閉じこもらせ、進んで環境に応じたり積極的に問題を解決していこうという気力を乏しくさせていたのではないかとも推論している。
Frischeisen-Kohlerも男子の対差は大部分の教科で女子をうわまわり、高学年になるにしたがって対差が大きくなる傾向を認めている。それがとくに際立ってくるのは、男子では8,9学年(14~16歳)、女子では7~9学年(13~16歳)であり、それは環境の影響を受けやすい成熟の始まりつつある年齢である、と述べている。また、女子の方が男子より早く成熟を開始するために、上記のような対差の特長が生じたのではないかと言っている。
われわれの研究結果によれば、一卵性ふたごの学業成績の対差は、男子の場合、中学校から高等学校にかけてさらに大きい上昇を続けている。Frischeisen-Kohlerの解釈を援用すれば、女子より成熟開始のおくれた男子は、高等学校年齢になって成熟が激しく発展し、学業成績に関していわば"Sturm und Drang"(疾風怒濤)の時期を迎えるのであろうか。これに反して、女子の場合、中学校から高等学校にかけて対差が小さく下降していくのは、早めに成熟開始した女子は、高等学年年齢になって成熟の速度が安定し、落ちつき、それが学業成績に反映するのではないかとも考えられる。
以上、ふたごの学業成績に関するわれわれの研究結果も含めたいままでの研究によると、学業成績に遺伝要因が関与することは明らかである。われわれの分析方法は、級内相関係数と対差を用いるふたつの方法であるが、ほぼ同一の結果がえられた。教科別では、保健体育、芸術は遺伝規定性が強く、数学は環境規定性が強い傾向が認められた。このことは、いままでの他の報告ともほぼ一致した結果である。対差に関して、中学校から高等学校への推移に男女差がみられたのは興味ある知見である。
しかし、以下のように男子と女子を別々にみていくと、いま述べたことはみかけ上のことで、男子と女子の対差の推移はそれぞれ特長のあることが分るのである。岩下の結果によると、小学校から中学校にかけて男子は0.16から0.22(その差0.06)、女子は0.11から0.20(その差0.09)で、女子の対差の上昇が著しい。本研究結果を男女別にみると、全教科について男子は0.691(中学校)から0.743(高等学校)へと対差は大きくなっているのに対し、女子では0.652(中学)から0.593(高校)へと小さくなっているのが対照的である(第7図の右)。男子では中学から高校にかけて対差が上昇しているのは8教科中4教科、下降しているのが4教科である。女子では8教科中7教科の対差が下降している。
岩下の結果と今回の研究結果をつなげて、小学校、中学校、高等学校へと対差の変化を推定してみると、男は小学校、中学校、高等学校へと漸次対差が上昇していき、しかも常に女子より大きい値を保っている。女子は小学校から中学校にかけて対差の上昇があり、しかもそれは男子の上昇率より高く、小学校の時の差より縮まるが、高校になるとむしろ対差は減少し、男子との差は大きくなる。
以上の、小学校、中学校、高等学校における学業成績の対差の男女差を含めた推移は、どう説明したらよいのだろうか。対差の男女差について、岩下は、ひとつは男女の性格の差によるものではないかと述べている。男子の場合、ふたごのおたがいが個性的で独自性が強ければ、学業成績の対差が大きくなることが予想される。さらに、岩下は当時の日本社会の男子専制の封建制が女子をして遺伝のからに閉じこもらせ、進んで環境に応じたり積極的に問題を解決していこうという気力を乏しくさせていたのではないかとも推論している。
Frischeisen-Kohlerも男子の対差は大部分の教科で女子をうわまわり、高学年になるにしたがって対差が大きくなる傾向を認めている。それがとくに際立ってくるのは、男子では8,9学年(14~16歳)、女子では7~9学年(13~16歳)であり、それは環境の影響を受けやすい成熟の始まりつつある年齢である、と述べている。また、女子の方が男子より早く成熟を開始するために、上記のような対差の特長が生じたのではないかと言っている。
われわれの研究結果によれば、一卵性ふたごの学業成績の対差は、男子の場合、中学校から高等学校にかけてさらに大きい上昇を続けている。Frischeisen-Kohlerの解釈を援用すれば、女子より成熟開始のおくれた男子は、高等学校年齢になって成熟が激しく発展し、学業成績に関していわば"Sturm und Drang"(疾風怒濤)の時期を迎えるのであろうか。これに反して、女子の場合、中学校から高等学校にかけて対差が小さく下降していくのは、早めに成熟開始した女子は、高等学年年齢になって成熟の速度が安定し、落ちつき、それが学業成績に反映するのではないかとも考えられる。
以上、ふたごの学業成績に関するわれわれの研究結果も含めたいままでの研究によると、学業成績に遺伝要因が関与することは明らかである。われわれの分析方法は、級内相関係数と対差を用いるふたつの方法であるが、ほぼ同一の結果がえられた。教科別では、保健体育、芸術は遺伝規定性が強く、数学は環境規定性が強い傾向が認められた。このことは、いままでの他の報告ともほぼ一致した結果である。対差に関して、中学校から高等学校への推移に男女差がみられたのは興味ある知見である。
