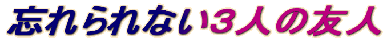 三浦光宏 JA山梨厚生連 文集「清流」 平成4年掲載
三浦光宏 JA山梨厚生連 文集「清流」 平成4年掲載
 戻る
戻る
清流原稿募集の時期が来た。去年の今頃も残暑が厳しかった。
放射線技師長だったK・K君の命日を9月10日に迎え、1年前の家族にとっても本会にとっても、余りにも大きかったあの衝撃を思い出さずにいれない。
39歳という若さで彼が他界する1週間ほど前、センターのソファーの所で何やら看護婦さんと深刻そうに話し込んでいるので、「どうしたの?!」と聞いてみると、「この頃血圧が高いので看護婦さんに相談しているところです。」という。「どのくらいあるの。」と聞くと「130の80です。」と答えた。「なんだ!」ひとつも高くないんじゃあないか、ぼくなんか130の90ぐらいあるよ。」というと「ぼくはいつも110の70ぐらいなんです。」と答えた。そばにいた看護婦さんも「血圧は日によっても、時間によっても変動しますから、この位では余り心配ないとおもいますがね。」と答えていたが、今になって考えると何か自覚症状があったと思われる。何かよくない夢を見たりして、友人にそれを話したり、いろいろ健康上不自然の現象があったように聞いている。

それから数日後の朝7時頃、事務所に行くと早朝にもかかわらず熱心にワープロを打っていた。「こんなに早くから何を頑張っているの」と聞くと「清流の文書です。」とうれしそうに答えた。その笑顔は自信に満ち、そして何かを完成した喜びと、その文章を見せたいような、もう少しとっておきたいような、何ともいえない複雑な笑みをみせていた。 私は用事があったので、「じゃあ頑張ってね!」とその場を去って行ったが、その2日後、彼は帰らぬ人となった。病名は心不全、誰も予期しない突然の死であった。
残された奥様と、まだ小学校のお嬢さん、息子さんの嘆きは想像を絶するものがあったと思われる。病院へ駆けつけ、葬儀終了までの3日間お世話をさせていただいたが、余りにも悲惨な出来事を目前にして私のショックも大きかった。
参事の計らいで奥さんに厚生連で働いていただくことになり、当時指導課長であった私が預かることになった。そして1年、彼女の献身的努力と暖かい仲間の中で、今では明るく元気に働いているのをみて、そっと胸をなで下ろすとともに、お子さまたちの健やかな成長を祈らずにいられない。
そんな年が明けた知事選の真っ最中だった翌年の1月、N・S課長から私の所に電話があった。用件は「腹が詰まって飯が食えない。今から厚生連に行くので見て欲しい。」ということだった。すぐさま手続きをとって診察してもらったが、医大のベットが空き次第即入院ということであった。1ヶ月もの長い検査期間を経て2月28日直腸の手術、そして闘病生活に入る。一時は職場復帰も果たし快方に向かったようにも思えたが、数ヶ月後再入院となってしまった。

それと重なるように、今度はY・K君が加納岩病院に入院、肝臓に腫瘍が出ての手術だった。手術後の彼は驚くほど元気であったが、3〜4週間経つうちに手術の疲れが出たのか体調が崩れていった。
同じ職場から同時に2人の友人が入院・手術を受け、時が経過する毎に誰の目にもそれが悪性の腫瘍だと気がつくようになった。病院への見舞いでその家族にもお会いする機会も増え、どう言葉をかけて良いのか解らず、心の苦しさや戸惑いがが増すばかりであった。
私にとってN・S、Y・S両君の奥さんは、かって同じ職場に働いていた仲間だけに、その気持ちはなおさらだった。できるだけ平静を装い、本人やご家族の心中を察して励ますしか、する術がなかった。
私は彼らの家族からの要望もあり、医療機関に勤めるものとして、厚生連や医大等の先生方のお力を拝借しながら、現在医学の最高水準の医療をかなえていただき、何とかして彼らを助けて頂きたい。もし、助けられないのなら、出き得るだけの延命と、激しい痛みを少しでも和らげていただきたいとお願いし、彼らのためにひたすら祈るのみであった。

現在医学の限界、これを考えるに、尊敬する医師の何人かが時には熱心のクリスチャンや、宗教家だったりすることから、あのように威厳に満ちた白衣の陰に」、医師として、人間としての諸々のご苦労や心労が隠されているのではないかと推察された。
私は、祖父母に大変大事に育てられたことから、先祖に対する思いは格別で、毎朝家を出かける前に必ず仏壇に向かって線香をあげることが日課となっている。それに加えて、そのころから般若心経の経本と、お数珠をポケットにお守りとして忍ばせるようになった。 般若心経は、世界で一番短いお経といわれている。父の知人である岡島の社長が、珍しい葡萄を見せにと京都の清水寺の館長を私の家にお連れしたが、その時のお礼の意味で般若心経を読んでいただいた。それがきっかけとなり、お経のカセットを購入し、心の迷いを浄土すべく勉強を始めたが、その教えは深く、そう簡単に理解出来得るものではない。しかし、その万分の一しか解らなくとも、ただひたすらお経を読むことにより救われるのは、仏教何千年かの歴史の資産かもしれない。私の宗教は先祖を家族の守護神として尊び祈る、最もポピュラーの宗教だと考えている。
癌と闘いながら、次第に衰弱していく彼ら友人を見舞うたびに、何とも言えぬ心の重ぐるしく感ずる日々であったが、病院に定期的に足を運ばずにいられない心境でもあった。
やがてN・S君が、家族の厚い介護の甲斐もなく他界した。享年45歳であった。その寂しさもまだ癒えない2ヶ月後の6月15日、今度はY・S君が他界してしまった。享年35歳、結婚8年目のご不幸だった。葬儀の時、幼い子供たちが無心に遊ぶのを見て涙を誘われた。
私はこの3人の死を、決して無駄にはしたくない。また、無駄にすることは出来ない。K・K君は心不全で余りにも突然の死であったし、N・S君は直腸癌が肝臓に転移したものであった。Y・S君もまた肝臓癌であった。
人間は動物と同様、自分の死を予期するという。そして病気には何らかの自覚症状があるともいう。自覚症状を感じたその時、専門医の診察を受けていたならと悔やまれるK・K君。人間ドックを受けて便に潜血反応があり、要精密検査といわれながらも忙しさに受診しなかったN・S君。職場検診を受けながら、超音波検診を受けなかったばかりに腫瘍が見つからず、進行してしまったY・S君。
何という運命のいたずらだろう。病魔はこうした小さな心の隙間に突然入り込んで職場からは優秀の人材と、家族からは夫、父親という大黒柱を奪ってしまったのである。彼らはいずれも、仕事に関しては優秀なスペシャリストであり、体は頑強で山登りやスキー、サッカーなどを愛するスポーツマンであった。
私は衛生管理者でもある。厚生連に出向以来「農協職場検診について」の研究を小林所長の指導で手掛け、一昨年秋、福島県で開催された第39回日本農村医学会で、農協・連合会には検診の結果「要精検」や「要治療」と判定された者について職場における就業上の措置や治療に関わるシステムがなく、職員が通院や入院による治療をしても職場に対する報告も義務づけられていない。
そのようなことから、職場の中には自分の健康を個人管理できずに治療が手遅れになっているケースが発生していること。従って、職場に健康管理者を設置すること。厚生連を軸とする職場検診の実施から事後指導に至るまでのシステム化の必要性、そして、労働安全規則第44条の職場検診の内容は最低基準で不備であることから、胃X線検査や超音波検診、さらに腎機能検査では尿素窒素やクレアチニンなどの検査項目を、大腸癌検診では便潜血検査等の検査項目を加え整備する必要があること。 労働年齢が延びている今日、健やかに老いるためには30歳からの健康管理が必要であることの提案を行い、具体的には中央会と協同して「職場健康管理規程」の作成に取り組み、農協への働きかけをしてきた。
しかし、その芽がまだ出ないうちに彼らは他界してしまった。残念でたまらない。私は彼らの検診結果も知らずに、彼らのために何も尽くしてあげられなかった。私のしてきたことは、いずれも病気が判明した後であって、この時ほど成人病、特に癌については、予防医学とともに、早期発見、早期治療が何よりも大事であることを苦い経験を持って思い知らされたのである。
私は自分の非力さを心から反省するとともに、このことを私の生涯の教訓として、これからも健康管理活動のために微力ながら、私の総力を持って取り組んでいきたいと思う
尊い友人であった3人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
合 掌
![]() 三浦光宏 JA山梨厚生連 文集「清流」 平成4年掲載
三浦光宏 JA山梨厚生連 文集「清流」 平成4年掲載
